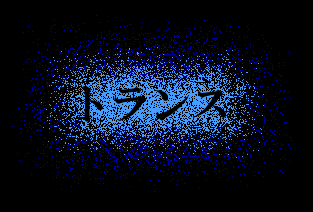第2話
池上先生が駒込にいる俺の元にやってきたのは、電話で話してから3時間半後のことだった。
途中の高速道路が事故渋滞していたのだと、池上先生は言っていた・・・気がする。
実は先生が目の前にやってきた時、俺は高熱を出して朦朧としていて、よく覚えていないのだ。
どうも寒気が引かず、身体がふらつくと思ったら、いつの間にか熱が出ていたらしい。
全くつくづく情けないというか、どうしようもない話だ。
俺という人間は、どこまで人に迷惑をかければ気が済むのだろう?
親に求められたことを兄弟で只一人上手くこなせず、諸事情あってこれ以上親元にいられないと思い極めて出てきてみても、結局一人では何も出来ない。
自分なりに色々と考え、その時々で必死にやってきたつもりではある。
しかし最低限自分自身が一人できちんと立てないのであれば、個人的努力などしていようがしていまいが、どちらでも同じだ ―― 結果を伴わない努力になど、何の意味も、価値もない。それはただの自己満足だ。
晴美さんに、龍二郎さんに、そして池上先生に次々と甘えて、迷惑をかけて、庇護されなければまともに生きてもいけない。
自分にはこれっぽっちも存在価値がないのだという気がした。
いや、“気がした”などというものではなく、それが紛れもない事実なのだろう・・・ ――――
「またなんか、つまらないことを考えてるだろ」
早朝に到着した家のベッドに俺を寝かせてくれながら、池上先生が笑った。
「・・・すみません、本当に・・・ご迷惑をかけて・・・」
熱のせいでぼんやりとしながら、俺は謝った。
「迷惑だなんて思ってないよ。ほら、スープ持ってきてやったから、少し飲みなさい」
「・・・いえ、俺は・・・」
「食べたくないだろうが、何かしら胃に入れないと薬が飲めない。一口でいいから、食べなきゃ駄目だ」
池上先生に言われ、俺は鉛を詰め込まれたように重い身体を必死で起こしてスープを何口か口に入れ、渡された薬を飲む。
たったそれだけのことで、とてつもない疲労を覚えた。
「・・・いい子だ」
薬を飲んだ俺の身体を再度ベッドに横たわらせてくれながら、池上先生が言った。
「とにかく今は何も考えないで、眠りなさい」
もう一度謝罪とお礼の言葉を口にしようとした俺だったが、上手くしゃべることが出来ない。
仕方なくただ小さく頷いて、俺は目を閉じた。
![]()
結局熱が引いて本調子に戻るのに、1週間以上もの時間がかかってしまった。
先生は俺がベッドに起きあがれるようになるや否や、塾のテストの採点やら何やらをしてくれるように頼んできた。
病み上がりなのにこき使って悪いな。
でも葛原は分かってると思うけど、夏休みは追い込みの時期だから、猫の手も借りたいくらいに忙しいんだよ。
と、先生は言ったが、もちろんそれは俺に余計な気を遣わせない為の気遣いに違いなかった。
しかしそれを分かっていても、次々と色々な ―― テストの採点やら、授業教材の下準備やら ―― を頼まれて、何かしていられるのは有り難かった。
黙っていると、考えたくない、考えても仕方のないことをぐるぐると考えてしまいそうだったから。
もしかしたら先生はそういう俺の精神状態を見抜いた上で、仕事を頼んでくれていたのかもしれない。
![]()
そのようにして、あっと言う間に1ヶ月半が過ぎた。
俺の身体の調子も完全に元通りになり、今後の事について真剣に考え出したのを見越したように、ある夜、池上先生が俺の元にやってきた。
「・・・ちょっと話、いいか?」
ノックの後にドアから顔を出した池上先生が、言った。
はい。と俺が頷くと、池上先生は部屋に入ってきた。
先生は6本パックになったハイネケン・ビールといくつかのスナック菓子を手にしており、俺にスナック菓子の袋の方を渡した。
そして床に腰を下ろし、ビールを包んでいる緑色の厚紙のパックを外しながら、楽しそうに笑う。
「こういう仕事をしていて感動するのってさ、生徒がいい学校に入れたとか、成績が上がったとかじゃないんだよな ―― や、もちろんそれだって嬉しいことは嬉しいんだけどな」
「・・・何です?」
スナック菓子の封を切りながら、俺は訊いた。
「うん、こうやって未成年だった生徒と酒を飲めるようになったとか・・・そういう些細なことの方が嬉しいっていうか、より感慨深かったりする」
と、先生は答えてビールを1本、俺に手渡してくれる。
「でも葛原は酒なんか、あんまり飲む機会なかったよな、きっと」
「いえ、そんなことありません ―― 実は家を出てしばらくホストをやっていたので、お酒は相当飲めるようになりました」
「はぁ!?ホストぉ?」
飲みかけたビールを危うく吐き出しそうになりながら、先生が俺を見た。
「はい、実は葛原の名前を捨てて一人立ちした方が、新宿でホスト・クラブを経営していらして。色々と話を聞きたくて訪ねていって、そのまましばらくお世話になっていたんです」
「・・・あー、なるほどねぇ・・・」
がしがしと後頭部をかきながら、先生は首を傾げる。
「しかしホストって・・・、葛原には向かないだろう、ああいうのは」
「・・・ええ、そうですね・・・、自分では分からなかったんですが、確かに向いてなかったんでしょうね」
と、答えながら思い出すのはもちろん、龍二郎さんの言葉だった。
―― お前、ホストはもうやめろ。お前はホストとか、そういった類の接客業には向いてねぇ ――
言葉を思い出すだけではなく、龍二郎さんの低い声の雰囲気や俺に触れる時のやり方の感触までもがいっしょくたになって蘇ってきて、俺は口をつぐむ。
胸の奥が、ひきつれるように痛むのを感じた。
「・・・そこでなんか、あったのか」
黙ってしまった俺の様子を伺うようにじっと見ながら、先生が訊いた。
視線だけを上げて先生を見て、俺は頷く。
「ええ、実は・・・、怪我を、して・・・」
「・・・させられたってことか?客に?」
と、訊いた先生は再び俺が頷くのを見て、深いため息をつく。
「事前にそういう気配や素振りなんかには、気付かなかったのか」
「ええ、全く」
「・・・ったく、危なっかしいなぁ葛原は、相変わらず」
再びやれやれというふうにため息をつき、先生は首を横に振る。
「でも彼女には一度も指名とかされたこと、なかったんですよ」
弁解するように、俺は言った。
「元々俺を指名してくれていたお客さんと一緒に何度か店に来ていた人でしたが、それだけで・・・無口な人で、話しかけてもろくに返事をしなくて ―― それが突然あんな・・・。
だから売り上げほしさに寝たとか、そんなのないんです。寝るどころか、話もろくにしたことがなかったんですよ、本当に!」
「 ―― 寝たなんてそんなこと一言も言ってないし、思ってないよ・・・、おいおい、どうしたんだ」
徐々に身を乗り出してまくしたてる俺の勢いに身を引いた先生が、不思議そうに眉を寄せた。