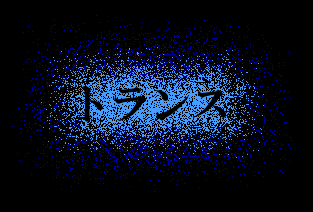第3話
一番最初に龍二郎さんが、
“寝てもいないホストを、刺したりしない”
と言って、俺の言うことを頭から信じてくれなかった時の口惜しさがフラッシュ・バックするように蘇ってきて、思わず興奮してしまったのに気付いた俺は、慌てて上体を元に戻す。
「・・・すみません、つい・・・」
と、言って俺はその場を誤魔化すように、ビールを口にした。
先生は俺の様子に腑に落ちないものを感じた風だったが、とりあえず順番に話を聞いていこうと思ったのだろう。そのまま話を続ける。
「・・・それで、怪我をして・・・それでも家には帰らなかったのか?」
「ええ、家には、その、色々と事情があって・・・特に今は、帰れないんです」
「帰れない? ―― と言って先生はぎゅっと顔をしかめた ―― なぁ、本人が言いたくないことを根掘り葉掘り訊くのは俺の本意じゃないが、こうなったからにはきちんと話せ。
どうして帰れないようなことになってるんだ」
「ええと・・・、あの、あんまり楽しい話にならないんですけれど」
「この流れから漫談みたいな話の展開をするなんて思ってないから、大丈夫だよ」
と、先生は言った。
それはそうだよな、と思った俺はひとつ息をつき、口を開く。
「 ―― 昔から俺の家は内部に様々な問題を抱えていて・・・、先生もそれは、ご存じでしたよね」
「・・・ああ、まぁ・・・うっすらとだけどな」
「そういうことに関して、俺が何をしようと意味などないことは、きっとずいぶん前から分かってはいたんです。でも ―― 俺が色々と上手くやれていないのがいけないのかもしれないと、そういう考えを捨て切れなかった。
それでずっと、自分なりに頑張り続けていたつもりでしたが、頑張りきれなくて、それで ―― なんか俺、少しおかしくなってしまって」
「・・・おかしくなったって、どんな風に?」
「なんだか、夜中に叫びだしてしまうようになったらしいんです。自分では全然、覚えていないんですけれど」
ビールの底の部分の一点を支点として缶をぐらぐら揺らしながら、俺は言った。
「父はこんな風になるなんて、世間体が悪いと・・・、お前の育て方が悪かったんだろうと、母を責めました。母はとにかくしっかりしてくれと言って、泣くばかりで ―― 俺も何とかしたかったのですが、自覚がないだけにどうしようもなくて・・・、結局精神科に通うしかないところまで、いってしまって」
「・・・、そうか・・・。
今はそういう発作は、治まっているんだな。ここに来てからそういうの、ないもんな」
「ええ、家を出て徐々に発作は治まりました。でも家に帰ったらぶり返すんじゃないかと思うと、悪くて」
「・・・、いや、悪いってお前・・・。
えー、ええと確かお前、兄弟いたよな?そっちから取り成してもらうとか、そういうのも無理そうなのか?」
と、先生は躊躇いがちに言った。
兄は2人とも俺と同じ学習塾に通っていた為、先生はその存在を知ってはいるのだ。
「兄たちは仕事柄不規則な生活をしていますから、俺の発作の騒動が仕事に差し支えるからと、家を出ました。
特に上の兄は少し前に結婚が決まって、俺の病気の件ではかなり神経質になっているらしくて。そういう意味でも俺は、あそこに帰るわけにはいかないんです」
出来る限り気を遣われないように、淡々と説明したつもりだったが、それでも先生はあぐね切った様子で俺を見た。
まぁ、それは当然と言えば当然だろう ―― 逆の立場であったら、こんな話を聞かされてとるべきリアクションなど、とても思いつけない。
「すみません、こんな話をして」
長引きそうになる沈黙を遮って、俺は言った。
「 ―― いや、葛原が謝ることじゃないが・・・。
しかしそんな状態で怪我をして、行く宛てもなくて・・・この数ヶ月、どうしてたんだ」
「怪我をしたときに、たまたま通りかかった人が助けてくれて ―― 実はその人にも言われたんです。俺はホスト向きじゃないから、やめろって」
「へぇ、そうなんだ」
「ええ。いくつかマンションを持っている人で、仕事が決まるまではそのひとつにいてもいいと言ってくれたんです。申し訳ないと思いつつも行くところがなかったので、ずっと甘えていた感じで」
「・・・そりゃあまた、ずいぶん奇特な人だな・・・、あー、ええと、念のために聞くが、変なことをされたり、要求されたりとかは・・・?」
「まさか・・・、そんなのは、全然ないです。
ただ、とにかく・・・本当に、親切な人で。こういう人もいるんだなって、何度も・・・、感動的というか ―― 夢・・・、みたいでした。
変な言い方に聞こえるかもしれないですが、あんなにはっきりとした“実体”としての存在を身近に、リアルに感じられた人は、初めてで・・・」
俺がとつとつと語るのを聞いていた先生は、そこでにっこりとした。
そして言う、「それで、好きになったんだ?」
「ええ、好きでした」、と俺は反射的に頷いて答え ―― そうしてみて今更、本当の意味で実感する。
そう、俺は龍二郎さんが好きだったのだ。
とてもとても、好きだったのだ。
「 ―― 喧嘩でも、したのか?」
少し間を空けた後で先生は訊き、引き寄せたティッシュの箱を俺に向けて差し出した。
そうされてみて初めて、俺は自分が泣いているのに気付く。
ここ2ヶ月近く、体内の砂漠化は進行するばかりという気がしていたので、まだ自分は泣けるのだと知って、驚いた。
慌てて頬を伝う涙を拭いながら、俺は首を横に振る。
「いえ、喧嘩というか、俺の父親のことがばれてしまって。それが知られたらおしまいだというのは、そもそもの始めから、分かっていたことでした。だからこそ・・・ ―― 」
「おいちょっと待て、お前の父親って、確か・・・」、と先生な激しく顔を歪める、「葛原、その、お前の好きな相手ってのは、一体・・・」
先生の空恐ろしげな、伺うような口調を聞いて、俺ははっと我に返る。
俺は最初から龍二郎さんの生業を知っていたし、助けてくれたということもあって、彼を怖いとか思ったことが一度もなかった。
その生業に関しても、当然ながらヤクザを全部が全部好きだとは言わないが、龍二郎さんがヤクザであるということは余り真剣に考えていなかった。
その為つい何の気なしに口にしてしまったのだが、良く考えてみれば(考えなくても)ヤクザに拾われてその人を好きになったなんて、普通に聞いたら驚くことかもしれない。
とは言え、今更もどうやっても誤魔化しようがなかったし ―― 龍二郎さんに対して抱いている気持ちを、誤魔化したりしたくなかった。
「・・・相手の人は、九竜会系の ―― 芳賀組の、男の人でした」
と、俺は言った。