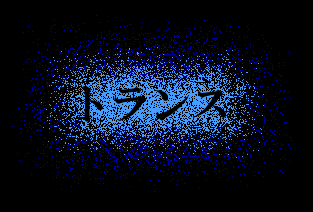第4話
「九竜会って ―― 芳賀組って・・・、葛原、お前・・・ ―――― 」
と、先生は言って、後は絶句した。
俺は何も言わなかった。
誤魔化すのも嫌だったが、それを同じくらい、言い訳するのも嫌だった。
長い長い沈黙の果て、先生はため息をつき、何度か左右に首を振った。
「ったく、本当に世間知らずというか何というか、全く、放っとけないよな葛原は・・・。
でもまぁ何はともあれ、そんな男と縁を切って来られたんだから、良かったよ」
と、先生は言い、再び深いため息をついた。
物事をいつでも、どんな時でも公平に、中立的な目で見てくれていた池上先生でさえ、俺と龍二郎さんの関係を認めてくれず ―― 関係を認めるどころか、会ったことすらない龍二郎さんのことを“そんな男”なんて言うんだな・・・。と思った俺は、悲しくなる。
龍二郎さんの背景が背景だけに、それは致し方ないことなのかもしれない。
先生だけが特別なのではなく、普通はそういう反応になるものなのだろう。それは頭では分かると思う。
でも、それでも、俺は・・・ ――――
「・・・先生がそう思われるのは、当然なのかもしれませんけれど・・・、でも本当に優しい人だったんです。ヤクザだとかそういうことがどうでもよくなるくらい、いい人だった。本当なんですよ、先生も彼に会えばすぐに分かると思います、だって例えば俺が、」
「そんなことはどうでもいいんだ、葛原」
と、先生は厳しい口調で俺の言葉を遮った。
「 ―― なぁ葛原、お前は大量のユダヤ人を惨殺したナチス一党に所属していた全員が全員、悪人だったと思うか?残忍な独裁者であったというスターリンの信奉者は、アジア諸国の人々を蹂躙した旧日本軍は、数多くの無差別テロを繰り返しているアルカイーダは ―― そこに所属する全ての人間が、悪人揃いだと思うか?」
俺は答えられない。
真っ直ぐに俺を見据えて、先生は続ける。
「所属する団体の善し悪しを一旦脇に除けて対個人として話をしたとき、全ての人間が根っからの悪人じゃないことくらいは、俺にだって ―― 普通に想像力がある奴だったら、誰にだって分かる。
しかし重要なのはそこじゃないんだ、いいか、世間一般的に見た時に重要視されるのは、その人間がどこに所属しているかなんだ。所属している側の善悪、そこがなにより重要になってくる ―― 俺の言っていることは、分かるよな?」
「・・・、はい、それは・・・分かります・・・」
膝の上に置いた自分の指先に向かって、俺は言った。
先生の言うことは1から10まで正しいのだ ―― そこには俺が突っ込める隙など、一片たりともなかった。
龍二郎さんがヤクザだという事実はきっと今後も変わらず、世間から見たヤクザというものが忌み嫌われる団体であるというのも、半永久的に変わらないのだ。
誰に嫌われようが、相対的に見てそれが間違っていようが、側にいられればそれだけで構わなかった、と思う俺の思考の方こそが間違っているのだ、きっと ―― 世間一般的に見れば。
「・・・色々と辛いことやきついことが続いていたんだろうし、葛原の気持ちが分からないとか、信じられないとか、そんな風に言うつもりはない。
でも、その男のことは忘れた方がいい・・・忘れるのが、一番いい。もちろん、時間はかかるかもしれないけどな」
と、先生はゆっくりと、諭すように言った。
「 ―― とにかくあんまり深入りしないうちに連絡をくれて・・・ここへ来てくれて、本当に良かった」
答えるべき適当な言葉が思いつかなかったので、俺は黙って頷いた。
先生も頷き、壁の時計が午前0時をすぎているのを確認し、
「ああ、あっと言う間にこんな時間か ―― もう寝たほうがいいな」
と、言った。
俺は再び頷き、先生と一緒に空き缶やらなにやらを片づけてからおやすみの挨拶を交わし、それぞれの部屋に入った。
その後俺はすぐにベッドに入ったが、久々に飲んだアルコールの効果により、すぐにも訪れるだろうと思った眠りは、なかなかやって来てはくれなかった。
眠れぬまま暗闇を見つめていた俺は、当然のような流れで、龍二郎さんを想うことになる。
それは決して、珍しいことではなかった ―― この2ヶ月弱の間、真夜中のベッドで龍二郎さんのことを思い出して眠れなかった回数は、両手の指を全て使っても足りない。
温もりはもう隣にはないのに、どんなに日が経っても、心が冷えていかなかったのだ。
だがその日は ―― 先生に龍二郎さんの話をしたせいもあるのだろうか ―― いつにも増して、妙にリアルに龍二郎さんが恋しかった。
先生が言ったように龍二郎さんを忘れるには、相当長い時間がかかるに違いない ―― つくづくと俺は、そう思い知らされる。
けれど時の経過と共に、痛みや温もりの記憶が薄れてしまうのだと想像すると、それはそれで悲しいとも思った。
こうしていつまでも、いなばの白兎のように心がひりひりしている方が、忘れるよりもずっといいような気がした。
時が経ち、他の誰かを好きになることがあってもずっと、薄れてゆかない痛い記憶を隠し抱いて生きてゆくのも、どことなく自分らしい気もする・・・ ――――
そんなことを考えつつ、転々と寝返りをうっていた俺はやがてうっすらとした寒気を覚え、慌てて頭まで布団を被る。
また熱など出して、先生に厄介をかけるわけにはいかない。
俺は可能な限り小さく身体を縮めてきつく自分で自分の身体を抱き、とにかく早く眠ろうと努めた。
だが努力すればするほど眠りの気配は遠のき、意識はクリアになってゆき ―― 冴え渡った脳裏の奥底にはいつまでも、微弱な寒気が流れ続けた。